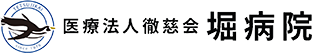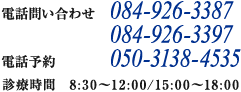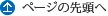今回のコラムは「めまい?眩暈?目眩?めまいの語源」です。めまいという言葉はいつから始まったのでしょうか、それを探ってみました。
<コラム17> めまい? 眩暈? 目眩? めまいの語源
めまいとは?
めまいは、広辞苑によると「目眩・眩暈:目がまわること,目がくらむこと。げんうん」と書かれています。漢字の「眩」は「くらむ」とも読み、「目がくらむ、目まいがする」の意味をもち、眩惑とか眩人(手品師)として用いられます。「暈」は「かさ、ぼかす」とも読み、「月や灯火の周囲にうすく現れる光の輪」、これから「月のかさのように周辺に向かつて次第にぼかす」、「めまい、目がまわる」の意味があります。
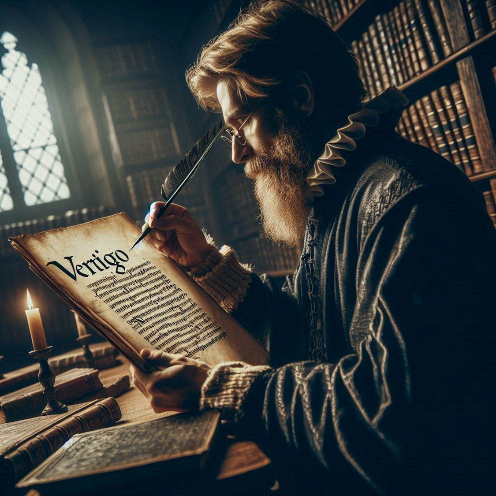 平安時代には多分「めまい/ひ」という言葉はなく,「くるめく」とか「くるべく」と表現されていたようです。この「くる」はくるくる回るの意で,しばしば「めくるめく」と用いられます。日本の古書では,「眼の前のものが揺れ動いて、あたかも鴨居に懸けた物がゆらゆらとして定まらないと言った感じ」を眩としています。
平安時代には多分「めまい/ひ」という言葉はなく,「くるめく」とか「くるべく」と表現されていたようです。この「くる」はくるくる回るの意で,しばしば「めくるめく」と用いられます。日本の古書では,「眼の前のものが揺れ動いて、あたかも鴨居に懸けた物がゆらゆらとして定まらないと言った感じ」を眩としています。
和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)は、日本の平安時代に編纂された百科事典であり、日本の古典文学の一つです。その中で、「眩(くら)」に関する記述が見られます。 具体的には、
「釋名云眩〈音懸女久流米久夜万比〉懸也目㪽視動乱如懸物揺々然不定也」
「書き下し分:釈名に云はく、眩〈音は懸、女久流米久夜万比(めくるめくやまひ)〉は懸なり、目の視る所、動き乱るること物を懸くるが如く揺揺然として定まらざるなりといふ」
とあるように、“眩” は「女久流女久夜万比(めくるめくやまひ)」と書かれていますので、これを縮めて“眩”の状態を“め”+“まひ(い)”というようになったようです。現代用語に置き換えると、目+舞いで「目が舞う」という意味になります。ここでいう「舞う」には「回る」という意味も含まれます。すなわち、グルグル回る回転性のめまい、フワフワふらつく浮動性のめまいや立ちくらみなど、すべての症状を総称して“めまい”と呼んでいます。
それでは、現代ではどうでしょうか?今では「めまい」はひらがなで表記することが多く、眩暈や目眩と書くことは少なくなっています。日本語では“めまい”という一つの単語しかありませんが、英語では回転するように感じるめまいの症状をVertigo(バーティゴ)、それ以外のめまいの症状をDizziness(ディジネス)と使い分けて呼んでいます。医学的にめまいというと色々な状態を含んでいますが現在、めまいの国際的な学会であるバラニー学会の分類では、Vertigo(自己回転感のあるめまい)、Dizziness(自己回転感の不明確な空間識の障害)、Vestibulo-visual symptoms(前庭覚−視覚性症状)、Postural symptoms(姿勢症状)の4つに分類されています。ただ、この分類は日本人には分かりにくいこともあるので、一般的には次のようなものが使用されています。
「めまい」の分類
回転性めまい(vertigo)
自分の身体または大地があたかも回転しているかのような感覚です。激しい嘔気を感じることがあり、体のバランスを失って倒れることもあります。三半規管、前庭神経、脳幹の異常など前庭神経核より末梢の障害、多くは耳の障害で生じます。
浮動性めまい(dizziness)
よろめくような、非回転性のふらつき感です。回転性めまいの回復期や脳幹、小脳の異常、高血圧などで生じます。
立ちくらみ(faintness)
血の気が引き、意識の遠くなる感覚。実際に失神に至ることもあります。起立性低血圧の代表的な症状であるほか、アダムス・ストークス症候群, 血管迷走神経反射、器質的心疾患・大血管疾患でもみられます。
平衡機能障害(dysequilibrium)
立ち上がったり起き上がったりした時に、身体が傾いてしまう感覚です。反射系と中枢系の連携障害、体平衡系の異常によって起こります。
めまいがするとの訴えで、患者さんは来院されますが、その「めまい」にはこれまで説明したような様々な状態があります。患者さんの「めまい」が実際にはどのような状態であるのかを、患者さんの話を聞きながら確認して、色々な検査を行って診断する必要があります。めまいに悩まれる時は、それがどのようなめまいであっても一度「めまいセンター」を受診してみてください。