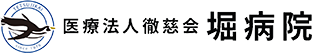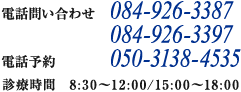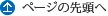最初に、「めまいが治るとは」を考える前に、めまいも病気の一つですから、病気が治るとはどういうことかについて考えてみましょう。
病気が治る
「病気が治る」とは、医学的、生理的、心理的な観点から捉えることができます。それを具体的に解説すると以下のような意味を持ちます:
- 医学的な観点
①原因の除去
病気の原因となっているウイルス、細菌、または異常な細胞(例えば腫瘍)が体内から取り除かれる、または活動が抑えられる状態を指します。
例: 感染症の場合、病原体が抗生物質や免疫によって排除される。
②症状の消失
病気に伴う症状(痛み、炎症、発熱など)がなくなり、患者が快適に過ごせるようになること。
例: 骨折の場合、骨が元通りに回復し、痛みがなくなる。
- 生理的な観点
①身体機能の回復
病気によって低下した臓器や組織の機能が正常な状態に戻ること。
例: 心筋梗塞後、心臓のポンプ機能が十分に回復する。
②代謝や免疫の正常化
体内で異常だった代謝や免疫反応が通常の状態に戻ること。
例: 糖尿病の患者が血糖値を正常範囲内に保つことができるようになる。
- 心理的・社会的な観点
①主観的な健康感覚の回復
患者自身が「元気になった」「日常生活が問題なくおくれる」と感じること。これは医学的に「治癒」とされる前でも達成されることがあります。
例: 精神的な病の場合、患者がストレスを感じず、生活の質が向上する。
②社会的な適応の回復
病気のために制限されていた仕事や趣味、日常生活への参加が再び可能になること。
例: リハビリ後、職場に復帰できるようになる。
このように「病気が治る」とは単純に症状がなくなることだけではなく、原因の解消、機能の回復、そして患者の生活の質が向上することを含む、多面的な状態を指します。そのため、治癒の定義は病気の種類や患者の状態によって異なります。
大きな違いは、「急性疾患」と「慢性疾患」ですので、それぞれに分けて説明します。
1.急性疾患の場合
急性疾患は、短期間で急激に発症し、比較的短い期間で治癒する病気を指します。例えば、風邪やインフルエンザなどが急性疾患に該当します。急性疾患の治癒とは、以下のような状態です。風邪やインフルエンザのような急性疾患では、完全に治癒することが多いので、薬を全く必要としない状態に戻ります。例えば、感染症が治癒すると、病原体が体から排除され、症状が消失し、薬を続ける必要がなくなります。
➀完全な回復: 症状が完全になくなり、病原体が体から排除される。
②機能の回復: 体の正常な機能が取り戻され、通常の日常活動ができるようになる。
2.慢性疾患の場合
慢性疾患は、長期間にわたって持続する病気で、しばしば一生涯にわたって管理が必要です。例えば、糖尿病や高血圧、関節炎などが慢性疾患に該当します。慢性疾患の治癒とは少し異なり、主に以下のような状態を指します。
慢性疾患では、病気の管理や症状の抑制のために、長期間にわたって薬を服用する必要がある場合があります。このような場合、「治癒」というよりも「症状の管理」や「安定した状態」が目標となります。例えば、糖尿病や高血圧などの慢性疾患では、薬の継続的な使用が重要です。
➀症状の管理: 病気の進行を抑え、症状を効果的に管理できる状態に保つ。
②生活の質の向上: 病気と共に生活を続けながら、できるだけ快適な生活を送るための対策や治療が行われます。
慢性疾患においては、完全な治癒が難しい場合もありますが、治療や生活習慣の改善によって、症状を緩和し、生活の質を高めることは可能です。
めまいが治る
それではめまいが治るとはどういう事でしょうか。めまいが「治る」とは、めまいの原因となる症状や疾患が改善し、以下のような状態が得られることを指します。
- めまいそのものの解消
めまいとは、平衡感覚に関わる異常によって「自分が回っているように感じる」「周囲が動いているように感じる」「ふらつく」などの症状が現れる状態です。これが解消するということは、めまいの発作や違和感がなくなり、日常生活に支障をきたさない状態に戻ることです。
- 原因となる疾患の治療
めまいの原因はさまざまで、以下のようなケースがあります。治るとは、これらの原因に適切に対処し、症状が改善することを指します。
- 内耳の異常(平衡感覚の中枢)
良性発作性頭位めまい症(BPPV):耳石の位置を元に戻す治療でめまいは消失します。
メニエール病:内リンパ水腫をコントロールする薬物療法や生活習慣の改善で発作は抑えられます。
- 脳や神経の異常
脳梗塞や脳出血:リハビリや薬物療法で神経の機能が回復し、めまいはなくなります。
小脳や前庭神経の疾患:炎症の治療やリハビリによって改善します。
- その他の原因
低血圧や貧血:原因となる血流や酸素供給の問題が解決されることで、めまいは治まります。
ストレスや自律神経の乱れ:リラクゼーションや心理療法で自律神経が安定し、症状は改善します。
- 再発防止と長期的な健康状態の維持
めまいが「治る」ということには、再発のリスクを減らし、安定した体調を維持できることも含まれます。これには、生活習慣の見直しや、原因となる疾患がある場合にはその管理が必要です。
➀生活習慣の改善:規則正しい睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動。
②めまい体操やリハビリ:内耳や平衡感覚を鍛えるトレーニングを続ける。
- 心理的・感覚的な安定
めまいが続くと、不安や恐怖感が二次的な問題として現れることがあります。これが解消され、心理的にも「めまいの心配がない」と感じられる状態も「治る」の一部といえます。
結論
めまいが治るとは、症状が消失することだけでなく、その原因に応じた治療を受け、再発することなく、日常生活が快適におくれる状態に戻ったことを意味します。ちなみに、「日本めまい平衡医学会」ではめまい治療の評価の判定基準として以下のような基準を使用しています。これを参考にすれば、1年間めまいが起こらなかったら治ったと言えると思います。加えて、薬の必要がなくなる状態にまでなれば、患者さんもめまいが治ったと実感していただけると思います。これからもめまいが治るように一緒に頑張りましょう。
参考
めまいに対する治療効果判定の基準案(メニエール病を中心に)
Equilibrium Res Suppl. 11 80-85, 1995
月平均めまい発作の頻度を治療前6カ月と治療後12カ月で比較する。
めまい係数=〔治療後12か月の月平均発作回数/治療前6か月の月平均発作回数〕x 100
このめまい係数により5段階に判定する
0:著明改善、1~40:改善、41~80:軽度改善、81~120:不変、>120:悪化
この際、治療前観察期間が6カ月に満たない時、治療後観察期間が12カ月に満たないときには、それぞれ観察期間を記入し、月平均発作回数で比較する。